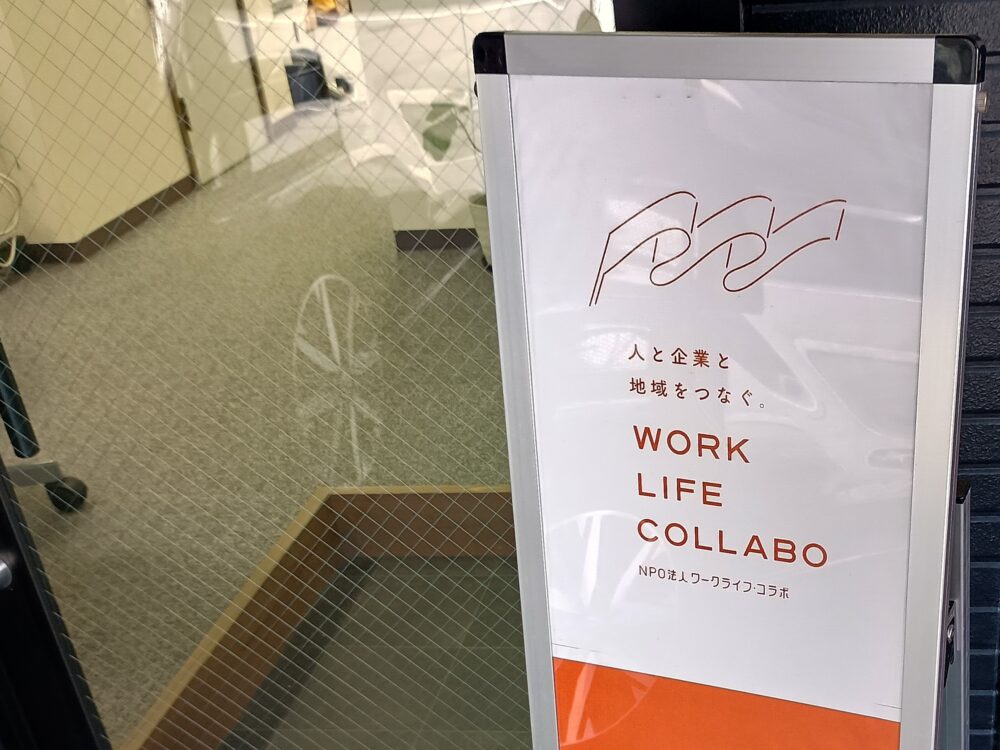デジタルスキルが生き方を拓く|可能性は誰にでも

話し手|デジタルハリウッドSTUDIO松山 コミュニティマネージャー 味村 和哉 さん
デジタルスキルを学びながら、新たな働き方や生き方に踏み出す喜びを共有できる場所。時代が動く最前線の空気に触れたくて、お話をうかがいに行きました。今日の話し手は、デジタルハリウッドSTUDIO松山の 味村 和哉(みむら かずや)さんです。

デジタルハリウッドはデジタル人材を育成する教育機関。大学や大学院のほか、STUDIOと呼ばれる専門スクールなどを運営されていますが、その現場で、今、何が起きているのでしょうか。
デジタルハリウッドに込められた想い
-どうしても、デジタルハリウッドという名前の由来をうかがいたくなります。
「ハリウッドでの映画づくりは、作品ごとに、監督、スタッフ、俳優たちが集まって仕事をします。ハリウッドという会社があるわけではないですよね。同じように、組織単位ではなく、プロジェクトで人が集まるような働き方を広げたいというのが最初の想いなんです。」
-デジタルスキルでそれが可能になると。
「デジタルハリウッドのスタートは1994年。まだ、Windows95普及前のネット黎明期でしたが、開学メンバーは、パソコンとインターネットでそうした新しい働き方が可能になると見通していました。プロジェクト主導の自由な働き方が実現できるように、デジタルスキルを身に付けた人材を育てる社会人向けの塾が、デジタルハリウッドのSTUDIOになります。」

-ハリウッドという、失礼ながら一見キラキラした名前の裏に、そんな新しい働き方のビジョンがあったとは知りませんでした。
ミッションは課題解決につながる人材の育成
-ご自身は、エンジニアとかプログラマーとか、デジタル畑の人なのですか。
「若いころから興味があったのは人材育成です。東京で20年ほど働いていましたが、理系や技術系とはあまり縁のない仕事でした。」
-デジタルへの思い入れがあって今のお仕事に就かれたというわけではないんですね。
「もともとは地方の出身でいずれは地元に帰りたいと思っていました。そんな時、偶然、デジタルハリウッドの求人広告を目にしたんです。教育や人材育成を通じて社会の課題解決につながる仕事をしたいとの想いがあったので、すぐに応募し、面接で、5年後には地元にデジタルハリウッドのSTUDIOを開設しますと宣言したところ、面白いヤツが来たと入社させてもらえました。」
-なかなかの新入社員だったようです。でも、宣言通り地元にSTUDIOを立ち上げてしまったのは、さすがにすごいですね。
地方こそ課題解決の最先端、デジタルでどこにいても成長できる
-地元に帰ると、時代のトレンドから離れてしまうとは思われませんでしたか。
「地方は課題の最先端だと思っていました。特に、人口減少に伴う社会の課題が真っ先に表面化するのが地方です。一方で、地方に行けば行くほど自分のことを伝えるのが苦手な人が多いという感覚もありました。」
-それらの解決にデジタルスキルが役立つんですね。
「デジタルスキルがあれば、時間や場所の制約を超えて世界と直結できます。また、デジタルスキルを使って物事をデザインする能力も大切です。デザインには地域の課題を解決できる力がありますが、そのためには、地方に真っ当なデザイナーがいることが重要だと思っています。常に学び続け、常に成長し続ける人がたくさんいる地域は絶対に廃れません。そうした人材を地方で育てていきたいですね。」

-終止、柔らかい笑顔を絶やさず、分かりやい言葉で丁寧に語る姿が印象的。人が学び育っていく過程に寄り添えることが楽しくて仕方ないといった様子です。
デジタル技術者ではなく、デジタル人材を育成
-STUDIOではどのようなことを学べますか。
「映像、Web、グラフィックデザインに関するデジタルスキルを習得できます。」
-そうしたスキルを学べるチャンネルは専門学校など数多くありますが、違いはありますか。
「三つのスキルがポイントになりますね。まずテクニカルスキル。デジタルを扱うのに必要な技術的な知識です。次にコミュニケーションスキル。仕事をうまく進めるには、自分の考えを理解してもらう技術、相手の考えを理解する技術、この両方が必要です。最後にコンセプチュアルスキル。物事の全体像を俯瞰してコンセプトを把握し構築できる能力で、これがないと単なる技術専門の人としか見てもらえません。デジタルハリウッドは、デジタルの技術者というよりは、デジタル人材を育てることを目指しているんです。」
現実の課題に向き合って身に付く実践力
-人材育成で大事にしていることは。
「クライアントが実際に抱えている課題を題材にして、クライアントは何を求めているのか、クライアントの先にいる顧客は何を考えどう行動する人たちなのか、クライアントの意向を実現するには何が問題でどうすれば解決につながるのか、と具体論で突き詰めていきます。机上の演習ではなく、それなりに社会経験のあるSTUDOの受講生に、現実のクライアントが直面している課題に向き合ってもらうことで、実践的な解決能力を培います。」
受講生の多くは現状を変えたい女性
-これまでの成果を聞かせてください。
「この4年で、10代から70代まで100人ほどが卒業しましたが、約6割は本人の希望に沿って新たな道に踏み出しています。残りの人たちも、STUDIOでの経験で、課題解決のヒントを見つける気づきの感度は上がったのではないかと思います。」
-受講者に何か特徴はありますか。
「受講生の約7割は今の働き方に満足できず何かを変えたいという人たちです。最初からデジタルデザインを志望しているのは3割くらいですね。デザイン志向がはっきりしている人たちはどこに行っても成長します。問題は現状を変えたい7割で、この人たちが自ら解決策を見つけられるように、成長を後押ししていかなければなりません。」
-何か行動を起こさなければ今の状況は変わらない。デジタルに可能性を感じて自らの意思で行動に移す受講生の皆さんの気持ち、とてもシンパシーを感じます。

-男女別ではどうでしょうか。
「受講生の7割が女性です。」
-それは興味深いですね。何か背景は見えてきますか。
「個人レベルの家事観や子育て観が、ひと昔前とは様変わりしています。年代が下るにつれ、家事シェアは当たり前、子育ては夫婦一緒に、という感覚です。一方で、そうした家庭のあり方に対応した、会社側の受入体制がまだまだ追いついていないという印象です。家庭と働き方のギャップに直面しているのがまさに女性で、会社や仕事に縛られる自分の現状を変えようと行動を起こす動機になっているのではないでしょうか。」
-とても示唆に富むお話です。デジタル人材育成の現場のリアルと、男女の働き方の環境の違いがつながっているようですね。デジタルスキルで働き方の選択肢が広がれば、恩恵を受ける人は多くいるはずです。
アラウンド・シニア世代もまだまだ変われる
-デジタルスキルを活かしたフリーランスなどの働き方は、若い人たちのものだと思っている人もいます。私はシニア世代ですが、私のような世代にとっても活躍の余地はありますか。
「シニア世代にも潜在的なポテンシャルは十分ありますよ。確かに、新しくデジタルスキルを学ぶことについては、若い人に比べて、気力や理解力の面でしんどく感じられることがあるかもしれません。でも、社会での経験値の多さは説得力につながりますし、培われた人脈は新たな仕事をとる上で有利に働くなど、若い人にはないアドバンテージもあります。それに、フェイスブックやラインなどシニア世代は意外にSNSをよく見ています。発信する対象としても、シニア世代にはポテンシャルがあります。」
編集後記|デジタルスキルが働き方や生き方の可能性を広げる
デジタルスキルという新しい武器には、多くの人が抱える働き方や生き方の課題を解決する力と可能性を感じます。時代の方向性を実感しました。とともに、アラウンド・シニア世代にとっても、デジタルスキルは縁のない話どころか大きな可能性を秘めているとのこと。ちょっと頑張ってデジタルへの一歩を踏み出せば、その先にはワクワクする世界が広がっているようです。
考えることはよりよく生きること…貴重な思考のひとときをありがとうございました。
取材日 2025.06.07