ワークとライフは対立しない|値観を尊重し合える働き方へ
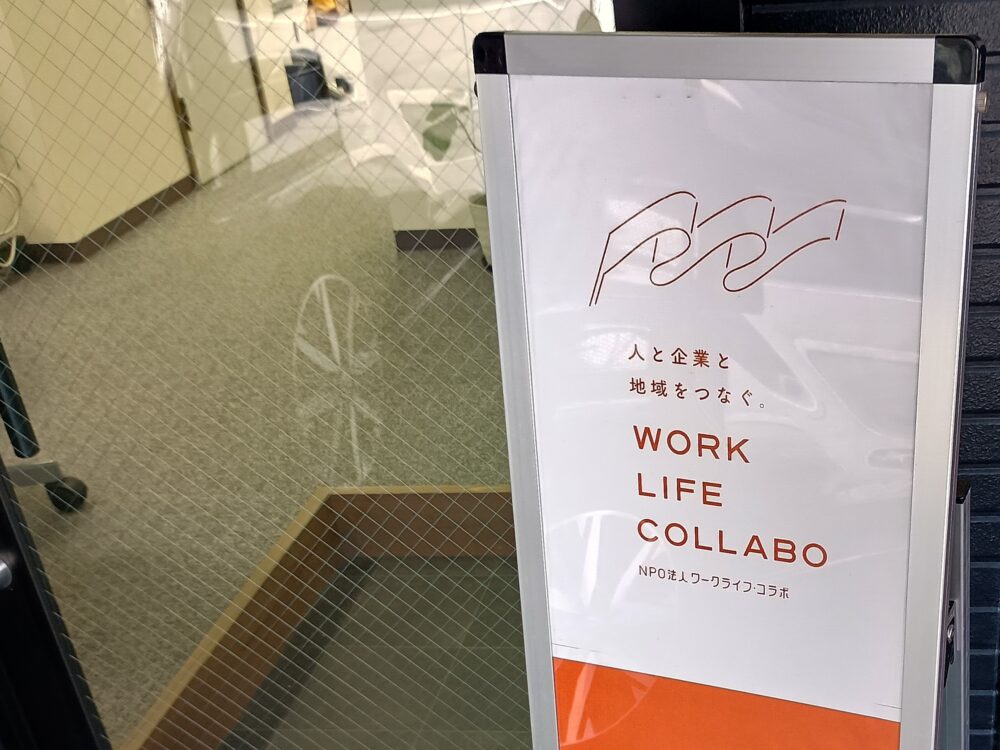
話し手|特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ 理事長 堀田 真奈 さん
働き方が変わることで、その人の暮らしや生き方も変わっていく。そんなメッセージに心を動かされ、お話をうかがいに行きました。今日の話し手は、ワークライフ・コラボの 堀田 真奈(ほった まな)さんです。

ワークライフ・コラボでは、働くことも暮らしのことも大切に考えられる人や会社を増やしたいと、企業の伴走支援や働き方改革の支援に取り組まれています。
仕事に対する価値観を尊重し合える風土づくり
「ワークライフバランスの話をすると、『俺は仕事第一、ワークワークバランスだ』とおっしゃる方もいますが、そうした個人の価値観まで変えようとは思っていません。企業には様々な考えや背景の人がいることを理解して、仕事に対する異なる価値観を尊重し合える企業の仕組みや風土を定着させることが大切だと思うんです。」
-てっきり、古い体質の人たちの考え方を変えようと活動されているのでは、という思い込みがありました。価値観の転換ではなく価値観の共存、それが基本姿勢のようです。
「ワーク」と「ライフ」は対立しない
-とは言え、育休の取得で労働時間が減ると業務に支障が出るととらえる向きもあり、一見、ワークとライフは対立する関係にあるようにも思われますが。
「一概にそうとも言えません。ワークの環境を整えることがライフの充実につながり、従業員のライフが充実すればワークの質の向上にもつながります。巡り巡って互いによい状態になるような仕組みを、企業の管理職や従業員が一緒になって考えていくことが大切ではないかと思います。」
-なるほど。ワークの充実とライフの充実は相乗関係にあるというわけですね。従業員、企業の一方に偏らず、双方にとっていい状態を目指す、そんなバランス感覚に、現場をよく見てこられた取り組みの蓄積を感じます。
スタートは、今そこにある困りごとから
-支援の相談を受けた企業には、どのような切り口で入っていくのですか。
「ワークライフバランスとは何か、から入るのではなく、まずは、人出が足りない、人員が定着しないなど、その企業が現に困っているポイントに着目します。その上で、①社会の制度はどうなっているか、②職場の現状はどのような状態か、③業務ではどんなツールを使っているか、というふうに、管理職や従業員の人たちとともに深堀りしていくと、その企業が抱えている働き方の課題がだんだんと見えてきます。」
-理念や理屈ではなく実態から入る。このアプローチが、現場目線の支援につながっているんですね。
ワークライフバランスの言葉は浸透したが視点のズレも
-ワークライフバランスや働き方改革という考え方は、既に多くの企業で一般化しているようにも思いますが。
「そうした言葉自体はほとんどの企業の方々がご存じですね。ただ、理解の仕方は様々で、『女性従業員はちゃんと育休をとっているんでうちは大丈夫。でも男性従業員に育休はいらんだろう』とおっしゃられる企業の方もおられました。」
-真意がうまく伝わり切れていないと。
「ワークライフバランス=子育て支援、あるいは、男性は育児をしないもの、という二つの思い込みがあるように感じます。今や若い世代にとってワークライフバランスは標準装備と言えます。企業の側が従業員の目線を知る努力をしないと、やがて人材が集まらなくなると心配しています。」

-流れるようなよどみない口調に自然に引き込まれます。理念先行ではなく、現場の実体験を大切にして、「今」の課題に誠実に向き合おうとする姿勢が素晴らしいです。
働き方の当事者は従業員だが、同時に企業側の問題でもある
-働き方の課題に向き合う中で心がけていることは。
「個々の従業員にとってどうかという視点とともに、企業にとってそれはどうなのか、という視点を外さないことがポイントだと思います。従業員にも企業にも双方に実利をもたらすと思ってもらうことが大切です。働き方と聞くと従業員の問題ととらえられがちですが、企業の側にも利益になるような解決策を丁寧に見つけていく姿勢で企業に寄り添っていくことで、私たちの取り組みへの信頼も得られていくように思います。」
従業員どうしの気づきを契機に、男女の育休や働きやすいマネジメントを実現
-これまでに印象に残った事例を聞かせてください。
「10年以上前になりますが、ある和菓子・洋菓子製造会社から相談を受けました。お菓子のエンドユーザーは女性が多いのに、会社の方針を決める管理職に女性がいないことに問題意識を感じているとのことでした。」
-まず取り組んだことは。
「従業員主体のプロジェクトチームを作りました。テーマは女性の能力が発揮できる職場づくり。最初は当事者である女性従業員だけで話し合っていましたが、そのうち、仕事に家庭にと女性だけが頑張るのはどこかおかしいのではないか、家事や育児など男性にも家庭での役割を担ってもらうことで、職場で女性が能力を発揮しにくい現状への理解も深まるのではないか、と議論が発展し、それでは、男性従業員もチームに入ってもらって一緒に議論しようということになりました。」
-話し合いを通じて、職場での女性の能力発揮と、家庭での男女の役割の偏りが、実はつながっているということに従業員自ら気づかれたんですね。
「プロジェクトチームでの議論を受けて、この企業さんでは、女性、男性に関わらず、子どもが生まれたら最低5日は義務的に育児休暇を取得しようという制度を作りました。これだけでも素晴らしいことでしたが、女性従業員が働きやすくなって良かったね、で終わらせるのではなく、実はもうひとつ狙いがありました。家事や育児を経験した男性従業員が増えて、女性が担ってきた家庭での役割の大変さに理解が深まれば、職場環境のマネジメントも変わってくるはずです。ワークライフバランスが、言葉だけでなくその企業の風土になることを期待しているんです。」
-従業員の自発性の中から解決のヒントを引き出して、企業の制度や仕組みにつなげるとともに、企業の風土として根付くところまで見据えて支援に関わっておられるんですね。ワークライフ・コラボの伴走支援の一貫したスタイルのようです。
働き方改革のキーパーソンは企業の中間層
-今後の活動の展開は。何かビジョンはありますか。
「企業の中間層に的を絞った人材育成の取り組みを進めたいと考えています。中間層の従業員は、部下や上司を巻き込んで自らがアクションを起こせる人たちであり、次につながる種を周りにまける人たちでもあります。ここをターゲットにして、より効率的、効果的にワークライフバランスの取り組みを広めていきたいですね。」
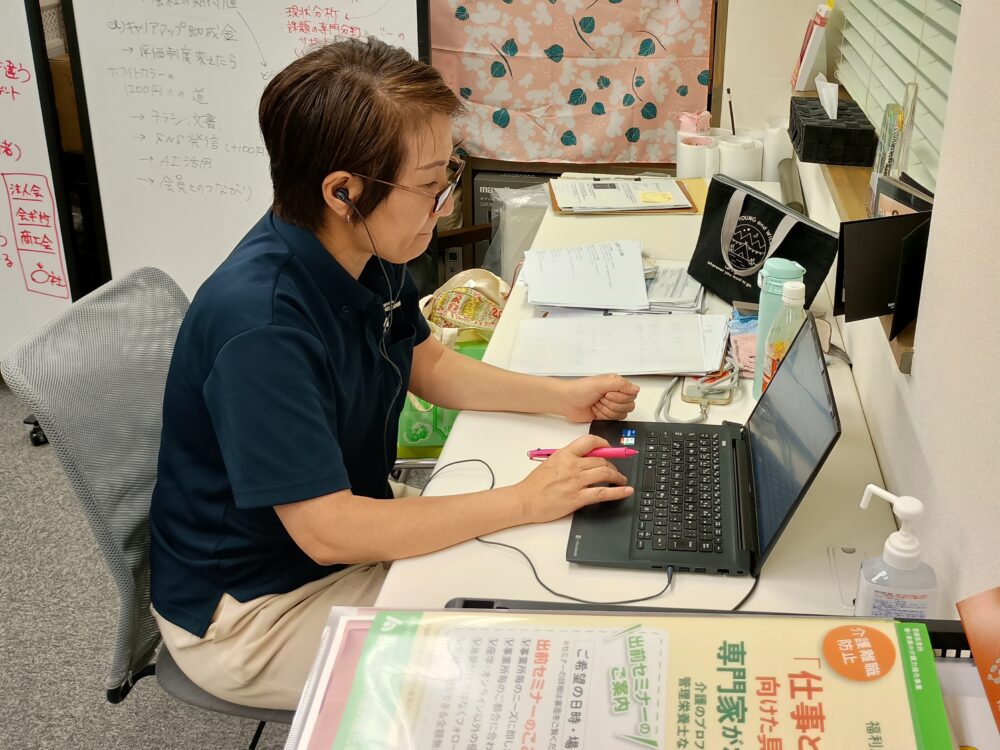
-インタビュー前後にも、リモート会議でスタッフの皆さんと2時間みっちり次の企画の打ち合わせをされていた堀田さん。気持ちの通じ合うスタッフと、いつでもどこでも建設的な会話ができる堀田さんの働き方そのものがとても魅力的で、大いに刺激をうけました。
編集後記|働き方と暮らし方。対立ではなく、ともによくなる仕組みや風土を
働き方と暮らし方は対立するものではなく、ともに良くなるような職場の仕組みや風土があるはず。それを、企業の人たちと一緒に考えていく…前向きでクリエイティブなお話でした。家事や育児が仕事と対立しない働き方は、今の私たちはもちろん、子どもたちの未来の暮らしにとっても大切なことではないかと思います。ワークライフバランス、分かった気になっていましたが、育休、時短、働き方改革といった言葉を本当の意味で理解していたか、改めて自分に問いかけるよい機会になりました。
考えることはよりよく生きること…貴重な思考のひとときをありがとうございました。
取材日 2025.05.22, 06.19
